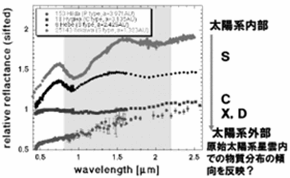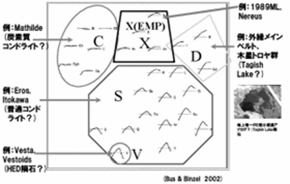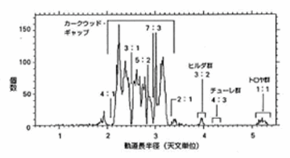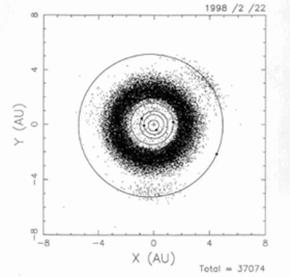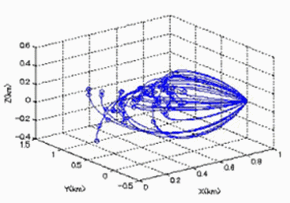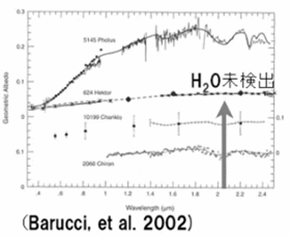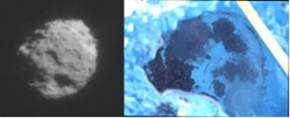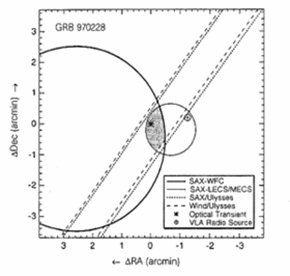次世代太陽系探査 - HTML:2014/09/05
You are here: Home / Future SSE Home / Post MUSES-C / 107P/Wilson Harrington
ソーラー電力セイル科学観測:トロヤ群およびメインベルト小惑星探査~
2003年第25回太陽系科学シンポジウム収録
矢野創、中村良介、横田康弘、長谷川直、安部正真、藤原顕(JAXA/ISAS)、出村裕英(会津大)、木下大輔(国立天文台)、H. Yano, R. Nakamura, Y. Yokota, S. Hasegawa, S. Abe, A. Fujiwara (JAXA/ISAS), H. Demura (Aizu Univ.), D. Kitnoshita (NAOJ)
1. 最も始原的な小惑星への初訪問
ソーラー電力セイルの利点として、燃料を持たずに木星領域ほどの日心距離に比較的早く到達できることが挙げられる。一般に「小惑星帯(メインベルト)」では日心距離に応じて主要なスペクトル型小惑星が占める割合が変化することが知られている(図 1)。最も火星に近い内側にS型、その外側に C 型と続き、木星に近づく外縁ほど、P(X)型・D 型と呼ばれるスペクトル型を持つ小惑星の存在度が増えていく(表 1)。それらは遠方に集中し、有機物に富んだ、最も始原的な小惑星と考えられいる。そのため詳細な地上観測をするには暗く、分光観測によるスペクトルもなだらかで、表面状態はまったくの未知である。
さらに地球上では Tagish Lake 隕石を除けば、まだ明らかなアナログ隕石が発見されていない(図 2)。むしろ微小な宇宙塵試料や一部の角礫岩隕石の混入物の中にこそ、その破片が含まれていると考える研究者もいる。いずれにせよ、表面物質が地球の生態系に問題を起こさないことがまだ判明していないこれらの天体からサンプルリターンを行う場合には、火星の地下土壌サンプルと同レベル、すなわち「バイオセーフティレベル(BSL)4 」級の「惑星検疫」施設と取り扱い方法が、COSPAR 惑星防御パネルから推奨されている。ゆえにはやぶさの直後にいきなりサンプルリターンを行うには、技術的な困難を伴う。
こうした謎の多い P / D 型小惑星に、まずはフライバイのみであっても史上初めて初訪問することができれば、「太陽系科学」および「宇宙生物学」へ大きな貢献をするミッションとなることは間違いない。すなわち前者については、長周期・短周期彗星、氷衛星、EKBO、センタタウルス天体、小惑星・彗星遷移天体(CAT 天体)とこれら「最も始原的な小惑星」の進化上の繋がり、後者については P / D 型小惑星を構成する物質と隕石・宇宙塵中で見つかる生命前駆物質や炭素質コンドライトとの関連・相違点、などを解明する手がかりが得られると期待される。このタイプの探査は、現在本ミッションとは独立に検討されている、ポストはやぶさ時代の小天体探査計画として有望視されている「スペクトル既知小惑星マルチサンプルリターン」構想とも、科学的に相補関係を持つことになる。
表 1:現在・将来の小天体サンプルリターンミッション.
| v [ mag. ] | a [ km ] | q | r [ AU ] | e | i [ deg. ] | P [ hour ] | |
| 87 Sylvia (P) | 6.94 | 260.94 | 0.0435 | 3.48716164 | 0.07946754 | 10.859095 | 5.184 |
| 153 Hilda (P) | 7.48 | 170.63 | 0.0618 | 3.97081876 | 0.14163911 | 7.837940 | 5.11 |
| 476 Hedwig (P) | 8.55 | 116.76 | 0.0493 | 2.65158463 | 0.07340614 | 10.951991 | 27.33 |
| 1212 Francette (P) | 9.54 | 82.13 | 0.0400 | 3.94963455 | 0.18814597 | 7.588326 | 16 |
2. 太陽・木星トロヤ群
一方、太陽・木星ラグランジュ点 L4 と L5 には、2001年5月時点でそれぞれ 623 個と 421 個、合計 1000 個以上もの小惑星の存在が確認されている。そこから想定される総数は 1 km 以上のものだけで ~1.6 X 105 個(Jewitt et al. 2000)程度であり、相互の衝突頻度はメインベルト小惑星の約 2 倍になると考えられている。これらの小惑星を総称して「トロヤ群」と呼ぶ。トロヤ群は木星との 1 : 1 の共鳴軌道にあるため(図 3)、木星公転軌道上の前後 60 度ずつ離れた安定な軌道を長く保っている(図 4)。もちろん、まだ探査機が訪れたことのない、人類未踏・未知の領域である。近年、木星から60度遅れた位置にある「 L5 点」のパトロクロス(617 Patroclus)はトロヤ群初の「連星系の小惑星」であることが確認された。この天体へのランデブーはさらに本ミッションの価値を高めるだろう。しかし現在までの軌道解析では、木星に60度先んじた位置にある「L4 点」の、例えばアキレス(588 Achilles)のほうが搭載機器に充てられる質量が大きく、探査機設計として分がある。実際、現時点のミッション検討では木星フライバイまでのノミナルミッションに続く「延長ミッション」という位置づけながら、これらトロヤ群の L4 点の複数の小惑星にフライバイ可能な軌道計画が複数成立しており、ΔV による選択の自由度がある(図 5,6)。
左(上)図 3:木星と共鳴軌道にある小惑星群.右(上)図 4:小惑星帯と木星トロヤ群の位置(最外円が木星公転軌道)
左(上)図 5:木星から L4 トロヤ群へのフライバイ軌道のオプション例.右(上)図 6:ソーラー電力セイルによる、L4 トロヤ群へのフライバイ(想像図)
なおトロヤ群にも D 型小惑星が極めて多いことが確認されている。これらが海王星領域以遠の「エッジワース・カイパーベルト天体(EKBO)」や土星・天王星領域の「センタウルス天体」との generic な関係にある起源を持つのかどうかが、大変興味深い。なぜなら 5 AU の位置で、2-3 倍、10 倍の日心距離にいる小天体の直接探査ができる可能性があるからである。特にアキレスは直径 120 km 超の巨大な小惑星であり、フライバイによる遠距離観測だけでも表面状態や地形の解明だけでなく、画像と軌道測距によるバルク密度の推定など、十分に成果を挙げることができる。一例では、トロヤ群はその安定した軌道位置から、木星の氷衛星のように太陽に一度もあぶられずに誕生・成長したとする仮説があるが、その表面のスペクトルからは水の吸収が発見されていない(図 7)。そこでバルク密度が推定できれば、内部に氷のような低密度の素材が詰まっているのかどうか、直接検証することがきでる。また表面のアルベドが低いのは宇宙風化を受けた有機物に覆われているとする仮説がある。ならばその表層は短周期彗星核との類似性を観察したり、一部で D 型小惑星の破片と目されるTagish Lake 隕石試料や宇宙塵試料との光学特性の比較を行うことは、きわめて重要である(図 8)。
左図 7:水の吸収が検出されないトロヤ群、外縁 D 型小惑星の連続スペクトル.右図 8:ヴィルド第二彗星核とTagish Lake 隕石
3. 観測装置:地形カメラ望遠鏡
小天体探査におけるその場計測装置は、基本的にははやぶさやのぞみなど、既存の探査機に搭載されたものをベースに出来る。ただし各探査対象によって異なる科学目標を達成するために必要な精度や仕様、バス側へのスペック・運用要求などによっては、同じ機能のものをアップグレードする必要がでてくる。
母船搭載の「地形カメラ」については、地質図(地形図)を作成するために,表面のきめが細かく見える解像度が必要である。そのため本来的には、航法用カメラを流用するのではなく、科学観測専用カメラが好ましい。特に NEAR シューメーカー探査機がエロス表面に軟着陸した際に撮像した、分解能数 cm の光学画像で、従来考えられていた以上の数の瓦礫(boulders)と、細粒のレゴリスが埋めたと思われるクレータ地形などが発見された。それらの生成機構を解明するには、さらに高分解能の近接画像で、個々のレゴリス粒子の粒系分布や形状、瓦礫表面の結晶構造や宇宙風化作用の程度まで評価できることが好ましい。しかしリソースが許さなければ、はやぶさ同様、「航法カメラ」望遠鏡(ONC-T)との共通化、科学観測用校正を行う必要が出てくる。
一般にフライバイミッションにおいては、多色測光観測はマルチバンドフィルターだとホイールを回転させるのに時間がかかって位相角や見かけの大きさが変わる。そこで、AOTF(音響光学素子)やLCTF(液晶フィルター)といった、連続多色測光観測装置の導入を検討する価値がある。それらは、スペクトル型が異なる複数の小惑星の観測を行う上で、機構部や重量を減らしつつ、最適波長で観測できる点も有利である。ところが本ミッション案では、5 AU 付近の D 型小惑星へのフライバイを想定している。この場合、面光源上の空間分解能を一定に確保しながら積分時間を稼ぐのは難しいため、各波長の強度を考えるとき、現在の AOTF 技術では光学系を大幅に明るくする技術的ブレイクスルーがない限り、本ミッションの要求仕様には耐えない。同様の理由で、太陽光を励起源とした蛍光X線分光観測も、5 AU のD型小惑星表面からの信号は極めて微弱なので、検出感度を大幅に上げるか、積分時間を長く稼がない限り、はやぶさや SELENE の延長線上には単純に考えられない。
それゆえに前項でも述べた通り、打上げ 10 年後に最終目的地のトロヤ群に着く以前に、小惑星帯や木星衛星などの複数の小天体にフライバイして、副次的な科学成果を増やす努力も、本ミッションでは極めて重要である。幸い、近年小惑星発見数は増加の一途をたどっており(2004年初頭現在で 25 万個を超える)、本ミッションの軌道計画の予備検討でも、クルージング時のフライバイによる複数の小天体探査は十分可能であるとの結果を得ている。
勿論、ランデブーによる全球観測を前提にした観測装置と、相対速度の高いまま行き過ぎる天体の観測に適した装置は、必ずしも同じではない。特にカメラでは視野角や積分時間のチューンアップに注意を払う必要がある。従来フライバイは全球観測ができないので科学的成果が低いとされてきたが、撮像カメラを当初から望遠鏡として設計し、ランデブー機より遠くから、少なくとも一自転周期より前から小惑星を面光源として連続でとらえることができれば、フライバイでも限定された分解能ながら全球観測が可能になる。トロヤ群フライバイでは、こうした観測装置のスペックの考え方が設計段階から必要になる。その際の長所・短所を考えてみる。これまでの惑星探査機のなかには、カメラとして広角と望遠の二種類を備えた例が複数存在する。ランデブータッチダウン型ミッションであるはやぶさの場合、理学観測用カメラは1種類(AMICA)であり、角度分解能は 96 [μrad] であった。しかし、ミッションの形態によっては、望遠/広角の二種類の光学系が必要となる可能性がある。
望遠光学系を搭載する長所は以下の 2 点である。
3 - 1. 高い空間分解能
望遠で得られる高い空間分解能は、天体表面地形のディテールを知る上で重要である。より小さなクレータまで分解できるため、多色測光カメラの場合には、宇宙風化の進行していない物質の多色測光データを取得できる可能性が高くなる。NEAR シューメーカー探査機が小惑星 Mathilde にフライバイした際、その最接近距離は 1,212 km であった。この距離の計画に際しては、天体重力で探査機の予定軌道を大幅にずらさないことも考慮されていた。ここで、フライバイ探査の場合について、NEAR の例と同程度の引力を受ける距離まで接近すると仮定して観測の空間分解能を見積もる。Mathilde の平均直径が約 53 km なので天体直径 10 km の場合に換算すると最接近時距離は約 100 km に相当する。角度分解能 100 μrad のカメラで観測すると、得られる最高の空間分解能 は10 m である。20 μrad で観測できれば 2 m に向上する。
口径 φ の望遠鏡で分解できる角度の理論的限界 ε は以下の式で表される。
ε=1.22 [rad] × λ / φ
ただし、λ は観測する光の波長 [ m ] であり、φは望遠鏡の有効径 [ m ] である。参考として、観測波長を 0.5、1.0、2.0 μm とした場合の、口径と理論分解能の関係を図 9 に示す。実際の口径を決める際には光量も考える必要があるため、この値は最小値である。
左図 9:口径と理論分解能の関係
3 - 2. 遠方からの観測が可能
より遠方から観測できれば、最接近時までの時間的余裕が多く取れる。このことは短時間で通り過ぎるフライバイ探査の場合に特に重要である。フライバイ時の観測可能時間についてここで簡単な見積もりを行う。便宜的に、直径 D [ km ] の天体を 5 ピクセル以上に見える距離を撮像限界距離 L [ km ] とする。距離 L から最接近するまでの期間を T [ sec ] とする。観測時間全体は 2T となる。L と T との関係は、おおよそ
L=D/(5×Δθ),
T=L/v
となる。ただし、Δθ はカメラの角度分解能 、v は探査機の相対速度である。仮に D = 10 [ km ]、v = 8 [ km / sec ] 、Δθ = 100 [ μ rad ]とした場合、L は 20,000 [ km ] であり、T は 2500 [ sec ](約 40 分)となる。一方、角度分解能を 5 倍細かい 20 [ μ rad ] にできれば、T は 5 倍の 12,500 [ sec ](約 3 時間半)確保できる。
観測時間が長くなれば、画像データを何度もデータレコーダに退避させる時間がとれるため、より多くのデータが取得できる。対象天体のなるべく多くの表層を観測するためには、観測時間 2T を天体自転周期の半分以上は確保することが望まれる。なお、最接近までの時間的余裕があれば、初期観測結果(位置・形状・自転軸・地質区分)に対する人間の判断を最接近時の観測計画にフィードバックする可能性もわずかながら残る。ただし猶予が 3 時間半あっても全部のコマンドを送り直すのは無理である。もしフィードバックを行うならば、(A)予めいくつか計画を用意して、直前に選択し直せるようにする、(B)いくつかのパラメータだけを直前に差し替え可能にしておく、など、設計当初からの対応が望まれる。
一方、望遠カメラを搭載する短所としては以下のようなことが考えられる。
3 - 2 - 1. 精密なポインティングが必要
視野が狭くなるため、精密なポインティングが必要になる。また天体に接近した際には天体の全体像を把握しにくい。おおよその天体形状や探査機との位置関係については、別の手段で(あるいは予め)把握しなければならない。このため、カメラとして望遠のみ搭載というやり方は考えにくく、広角カメラでカバーする必要がある。もちろん、広角カメラは接近過程の航法用にも役立つので、これを航法カメラ ONC - W と共通化することも検討すべきだろう。
3 - 2 - 2. 重量の増加
観測機器の重量は最も大きな問題になりうる。広角と望遠の二種類を持てば、一種類の場合に比べて当然重量が増える。また角度分解能を上げるには口径と焦点距離を大きくする必要があり、重量増につながる。具体的に達成可能な重量は今後工学的見地からの検討を要する。
以上の点を総合的に考慮すると、ミッションにおけるフライバイ観測の比率が大きくかつ重量に余裕がある場合は、望遠と広角の2種類の光学系を搭載するのが望ましいといえる。角度分解能は例えば各々 20、100 [ μ rad ] ということが考えられる。一方、ミッションがランデブー主体になる場合、または重量に余裕がない場合は、数 10~100 [ μ rad ] の多色測光カメラ一種類のみといった解となろう。背景放射・黄道光観測器と鏡体部分・光学系の共通化を測りつつ、検出部を分けるという設計が実現できれば、重量も幾分か抑制できるだろう。
Creating a better future by exploring other worlds and understanding our own.