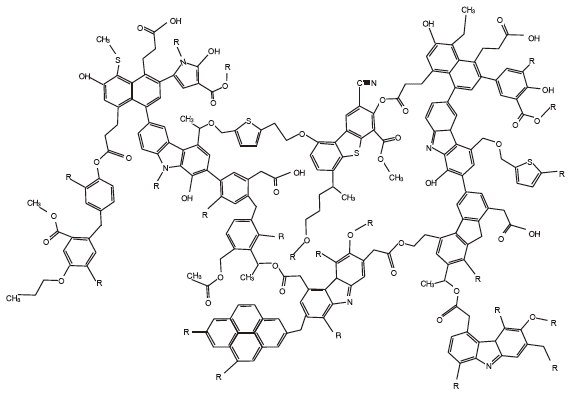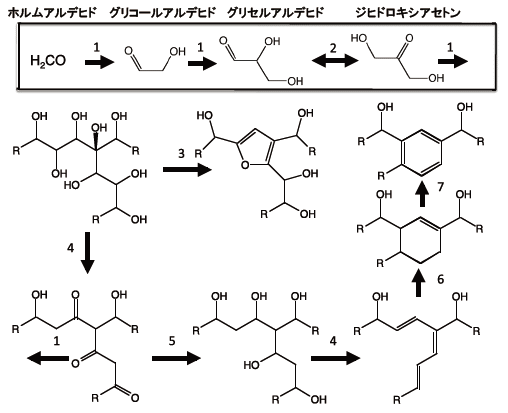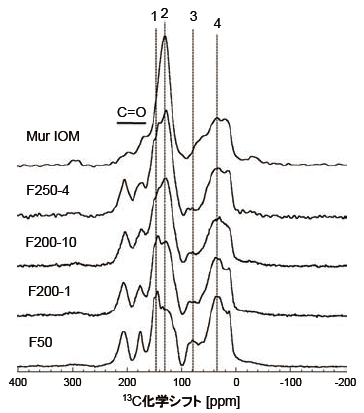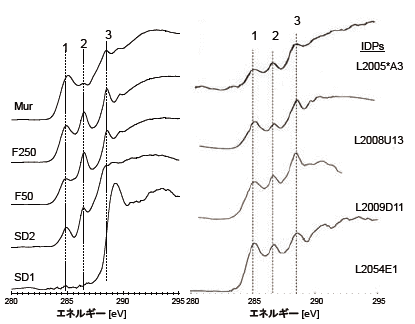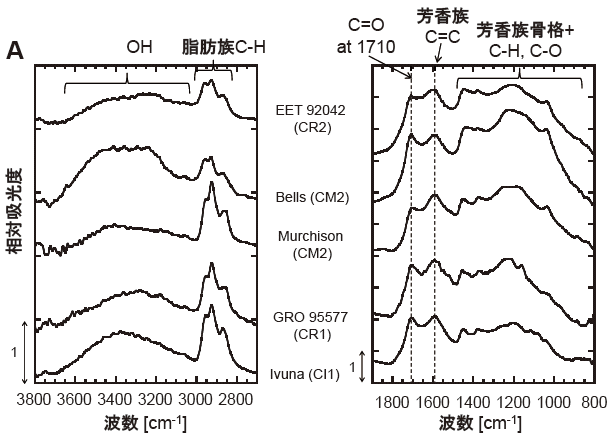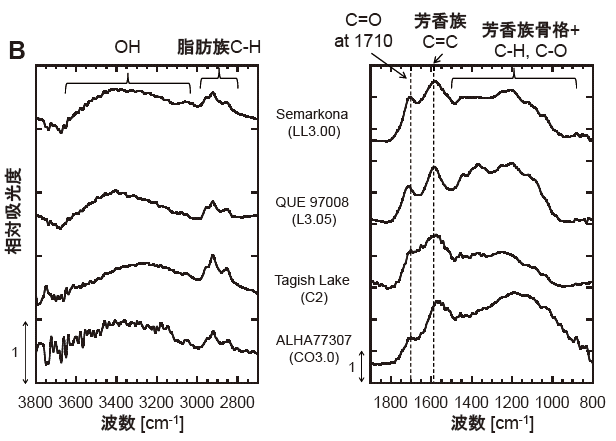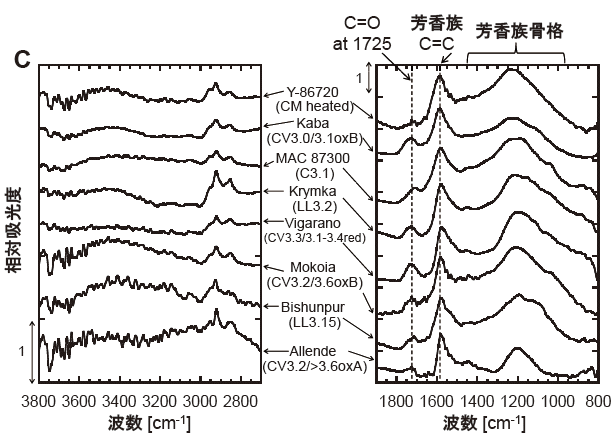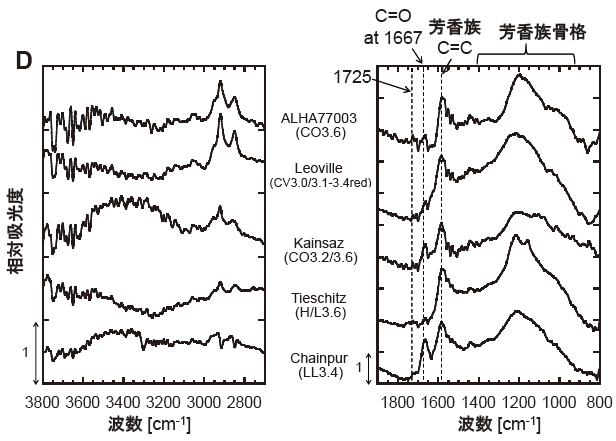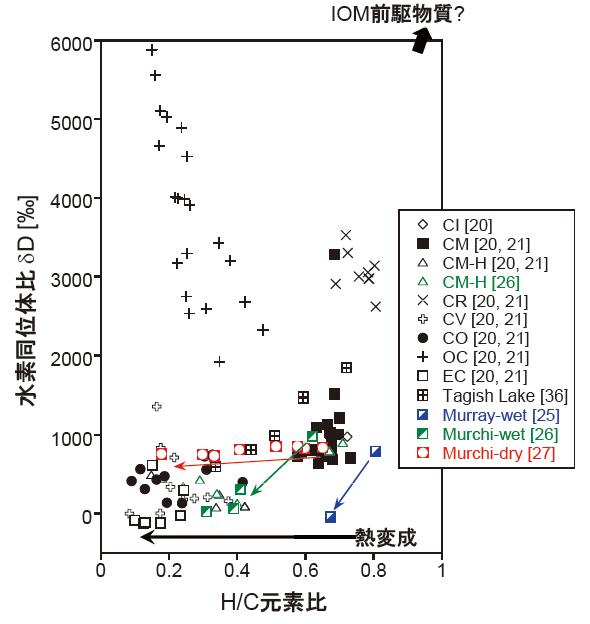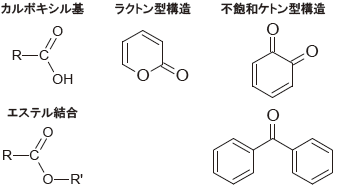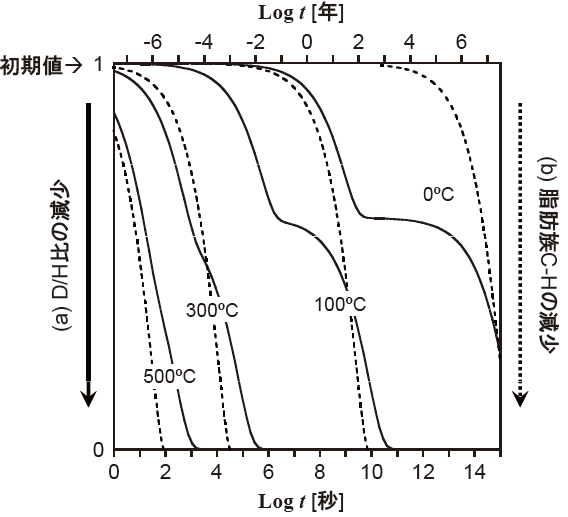次世代太陽系探査
太陽系形成・生命起源
不溶性有機物 IOM
不溶性有機物 IOM
始原天体有機物研究の今とこれから II. : October 15, 2016. Published
癸生川陽子 : カーネギー研究所(当時)
この遊星人記事は、日本惑星科学会遊星人編集専門委員会より許可を得て掲載しております。
要旨
隕石中の有機物の大部分は酸や溶媒に溶けない不溶性有機物(Insoluble Organic Matter, IOM)と呼ばれる複雑な高分子有機物からなっている.このような有機物は,芳香族骨格に脂肪族鎖や C = O 等の官能基が置換した分子構造を持ち,原始太陽系星雲や隕石母天体での化学的・熱的作用を受けることで,様々な化学構造変化を起こす.したがって,変成過程の痕跡を記録している隕石有機物を調べることは、太陽系形成初期の物質進化の解明に重要な役割を果たすことが期待される.本稿では,隕石有機物,特に IOM の起源と進化について,最近の研究結果をまとめてレヴューする.
1. はじめに
本論文は,隕石中の「不溶性有機物」を中心に,できる限り新しい研究結果を踏まえて,太陽系形成初期における有機物の起源と進化を包括的に捉えようと試みたつもりである.隕石中に見つかっている,アミノ酸に焦点を置いた近年の研究動向に関しては,薮田氏による「始原天体有機物研究の今とこれから I.アミノ酸」[1] を参考にして頂ければ幸いである.
始原的なコンドライト隕石には最大で数 wt % 程度の有機物が含まれており,その大部分(> 70 %)は不溶性有機物(Insoluble Organic Matter, IOM)と呼ばれる,複雑な高分子有機物である(図 1 [2]).この先は簡単のために IOM と記述する.
Image Caption :
図 1. Murchison 隕石の不溶性有機物(IOM)のモデル図.R は同様の有機構造のネットワークを表す.図の出典[2].
これらの有機物は原始太陽系星雲や隕石母天体での化学的・熱的作用を受けることで,H / C 比の減少や同位体比の変化等の様々な化学構造変化を起こす.したがって,変成過程で受けた痕跡を記録している隕石有機物を調べることは,太陽系形成の初期過程で起こった物質進化過程の解明に重要な役割を果たすことが期待される.IOM は HCl / HF あるいは CsF / HF 処理により無機成分を溶かした残差として回収される,黒っぽい粉末である.このような有機物の分離はかなり古くから行われていたようで,19 世紀末には Orgueil 隕石(CI1,1864年フランスに落下)から珪酸塩鉱物を溶かして炭質物が得られたという記録がある[3].本格的に隕石中の有機物に注目が集まったのは1969年,オーストラリアにMurchison 隕石(CM2)が落下して以降であろう.ちなみに同年は,メキシコに Allende 隕石(CV3)の落下,日本の南極探検隊による南極隕石の発見,そしてアポロ 11 ミッションによる月の岩石の回収など,惑星物質科学にとって重要な試料の当たり年であった.Hayatsu ら[4]は,熱分解・化学分解ガスクロマトグラフィーや赤外分光などの手法を用いて IOM を分析し,芳香族骨格に脂肪族鎖,COOH,OH,C = O といった官能基を持つ複雑な分子構造を持つことを確認した.今でも彼らの提案した基本的な分子構造は揺らいでいない.
2. 不溶性有機物(IOM)の起源
これまでに議論されてきた IOM の起源については諸説あるが,大きく二つに分けることができよう.一つは,星間空間あるいは原始太陽系円盤の外縁部の極低温環境で形成されたとする考えである.まず,分子雲コアでのイオン・分子反応に続き,星間塵に吸着した分子の粒子表面反応により低分子有機物(ギ酸,メタノール,ホルムアルデヒド等)が生成[5],さらに星間塵の氷マントル中でこれらの低分子有機物が紫外線外スペクトルの 3.4 μm バンド(脂肪族炭素の吸収領域)と IOM の赤外スペクトルとの一致も観測されている[8].さらに,重水素を含むイオン・分子反応は発熱反応であるため,極低温におけるイオン・分子反応では,有機物に重水素の濃集が起こる[9].15N についても同様である.したがって,IOM に見られる重水素や 15N の過剰は星間空間,あるいは原始太陽系円盤の外縁部起源であると考えられている[10].
二つめは,高温の原始太陽系星雲を起源とする説である.星雲中の CO 及び H2 ガスを出発物質としてメタン及び鎖状炭化水素を形成する,フィッシャー・トロプシュ反応:
CO + 3H2 → CH4 + H2O
を基とした重合反応により,炭化水素を含んだ複雑な高分子有機物が形成されるというものである[11].しかし,(a)IOM は芳香族炭化水素の割合が高いが,生成物には鎖状炭化水素が多い,(b)重水素の濃集を説明できない,(c)触媒となる金属や酸化物(例えばマグネタイトや鉄ニッケル合金など)と IOM との共存関係があまり見られない,といった理由によりあまり受け入れられていなかった.しかし,最近 Nuth ら[12]による,混合ガスに N2 を加え,フィッシャー・トロプシュ反応にハーバー・ボッシュ反応:
N2 + 3H2 → 2NH3
を組み合わせた実験により,再び注目を集めている.彼らの実験により,これまでは触媒効果を失わせてしまうと考えられていた,粒子表面への有機物のコーティングが自己触媒作用を持つことにより効果的に反応を進行させ,なおかつ,IOM のような窒素や芳香族炭化水素を含んだ複雑な高分子有機物を形成することが示唆された.
そして近年三つめとして Cody ら[13]により,ホルムアルデヒド(CH2O)を出発物質とするホルモース反応:
2CH2O → C2H4O2(グリコールアルデヒド)
― [CH2O] → C3H6O3(グリセルアルデヒド)― [nCH2O] → 糖類
を基にした重合反応(図 2)による,太陽系形成初期の始原天体における液体の水の存在下での IOM の形成が提案された.ホルムアルデヒドは星間空間や彗星からも見つかっていることから[14],このような始原天体におけるホルムアルデヒドの存在は充分に考えられる.また,星間空間に存在するホルムアルデヒドは重水素の割合が高いため[15],星間空間由来のホルムアルデヒドが始原天体に存在していたとすれば,IOM における重水素濃度の高さも説明できる.
Image Caption :
図 2. ホルモース反応及びそれに引き続き複雑な高分子有機物へと重合する過程の模式図.反応 1: ホルムアルデヒドの重合,反応 2: 分子内転移による異性化,反応 3: 脱水及び閉環反応によりフラン状構造の形成,反応 4: 脱水反応によりケトン(C = O)やオレフィン(C = C)構造の形成,反応 5: 還元反応,反応 6: 閉環反応,反応 7: 脱水素反応により芳香族構造の形成.図の出典[13].
核磁気共鳴(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)や X 線吸収端近傍構造(XANES)分析の結果をみると,Cody らの合成した高分子有機物は,始原的なコンドライト隕石に含まれる IOM と類似した分子構造を持っていることが分かる[13](図 3,図 4).さらに,系にアンモニアを加えることにより,低温での重合反応が速度論的に有利になり,なおかつ,IOM との分子構造レベルでの類似性が増すことが分かった[16].また,ホルムアルデヒドを基に重合された有機物には,スターダストミッションにより 81P/Wild 2 彗星から採集された塵や,彗星起源と考えられている惑星間塵(Interplanetary Dust Particle, IDP)に含まれる有機物との類似性も見られる[13]( 図 4).したがって,81P/Wild 2 彗星塵や IDP に含まれる有機物が元となって,隕石母天体での水質変成や熱変成を受けることで, 隕石有機物(IOM)へと進化していったのかもしれない.
Image Caption :
図 3. ホルムアルデヒドを出発物質として生成された高分子有機物及び Murchison 隕石の IOM の 13C - NMR スペクトル.50℃ で生成した有機物(F50)及び,F50 を 200℃ で 1 時間(F200 - 1),200℃ で 10 時間(F200 - 10),250℃ で 4 時間(F250 - 4),水熱したもの.1:エノール(OH が結合した二重結合炭素),2:芳香族またはオレフィン(C = C),3:アルコール(C - OH),4:メチン基(C - H).図の出典[13].
Image Caption :
図 4. ホルムアルデヒドを出発物質として生成された有機物(F50: 50°C で生成,F250: F50 をさらに水熱したもの),Murchison 隕石のIOM(Mur),81P/Wild2 彗星から採集さ れ た 塵(SD1,SD2), 惑 星 間 塵(Interplanetary dust particles,IDPs)の炭素 X 線吸収端近傍構造(C-XANES)スペクトル.1: オレフィン(C=C),2: 二重結合炭素に結合したケトン(C=C-C=O),3: カルボキシル(COOH).図の出典[13].
隕石有機物分析や天文観測,室内実験から,様々な IOM 形成のシナリオが提案されているが,複数の起源が寄与している可能性もあり,未だ IOM をはじめとした隕石有機物の起源は完全には解明されていない.いずれにせよ低分子有機物から高分子有機物へと進化してゆき,彗星に存在するような始原的なものから,水質変成や熱変成を経て,隕石にみられるような様々なバリエーションを持つ IOM へと進化していったと考えられる.隕石母天体での IOM の進化については以下の章で述べる.
3. 不溶性有機物(IOM)の進化
3 - 1. 水質変成
水質変成を受けた代表的な隕石グループは,CI,CM,CR 炭素質コンドライトである.これらの隕石はさらに,水質変成度の高いものから岩石学タイプ 1 ~ 3 に分けられる.例えば,岩石学タイプ 2 の CM コンドライトは CM2 というように記述する.これらの隕石の IOM の NMR 分析によると,CR2 < CI1 < CM2 の順でやや芳香族炭素の割合の増加がみられるが[17],赤外吸収スペクトル[18]( 図 5A),ラマンスペクトル[19],及び H / C 元素比[20,21](図 6)にはあまり差はみられない.IOM の熱分解生成物をガスクロマトグラフ質量分析法(GCMS)などにより詳細に分析すると,水質変成に伴い,エーテル結合(- O -)の減少や,芳香族部分のベンゼン環の数の減少などがみられるようである[22].また,IOM から熱水処理により分離されたアンモニアの量は大きく異なり,多いものから,GRA 9522(9 CR2)> Orguei(l CI1)> Murchison(CM2)> Ivuna(CI1)> Renazzo(CR2)> Bells(Unusual CM2)となっている[23].しかし,水質変成度の違い(岩石学タイプ)や隕石グループ間での系統的な変化は見られない.一方,IOM 中の水素同位体比(δD 値)は隕石グループ間で大きな違いが見られる[20,21](図 6).CR コンドライトでは高い値をとり,CM,CI コンドライトではやや低い値となっている.
まとめると,これらの隕石の IOM は,岩石学タイプによる系統的な変化はあまりみられず,むしろ隕石グループ間でやや違いがみられるようである.したがって,IOM の化学構造は,岩石学タイプにより示されるような水質変成度よりも,変成を受けた環境の違いを反映しているように思われる.
図 5A.
図 5B.
図 5C.
図 5D.
Image Caption :
図 5A - D. 様々なコンドライト IOM の赤外吸収スペクトル.スペクトルの特徴に基づき,A ~ D のグループに分けた.それぞれ左側: 3800 ~ 2700 cm-1,右側: 1900 ~ 800 cm-1.IOM の受けた熱履歴は A < B < C ≈ D と考えられる.なお,グループ C,D の一部に脂肪族 C - H が多くみられるが,原因として(a)芳香族 C = C のピーク高さでスペクトルを規格化しているため,グラフェン化が進み赤外活性な芳香族 C = C が減少するに従ってその他のピークが過大評価される,(b)有機汚染,の 2 つが考えられる.図の出典[18].
Image Caption :
図 6. 炭素質コンドライト(CI,CM,CR,CV,CO),普通コンドライト(OC),エンスタタイト・コンドライト(EC),加熱を受けた CM コンドライト(CM - H), 及び,Tagish Lake 隕石の IOM の水素同位体比(δD 値)と H / C 元素比のプロット.Murray 隕石 IOM を 300℃ で 6 日間水熱(Murray - wet[25]),Murchison 隕石 IOM を 270,300,330℃ で 3 日間水熱(Murchi - wet[26]), 及び,Murchison 隕石 IOM を不活性ガス雰囲気下で加熱(Murchi - dry[27])のデータも重ねてプロットした.図は[20,21]を改変.Tagish Lake は[36],Murray - wet は[25],Murchi - wet 及び CM - H は[26],Murchi - dry は[27]を引用.
3 - 2. 熱変成
熱変成を受けた代表的なコンドライト隕石のグループは,CV 及び CO 炭素質コンドライト,普通コンドライト(OC),エンスタタイト・コンドライト(EC)である.熱変成度の低いものから岩石学タイプ 3.0 ~ 6 に分けられる.これらの隕石は 200℃ 以上の高温を経験しており,低温(0.150℃)の水質変成を受けた隕石に比べ,IOM の分子構造に大きな変化が見られる.ラマン分光法や X 線吸収端近傍構造(XANES)分析によると,これらの IOM は熱変成に伴いグラフェン構造が発達したことが分かる[19,24].また赤外分光法を用いることにより,グラフェン構造だけでなく,熱変成に伴う各種有機官能基の減少を詳細に観測することができた[18](図 5).特に,カルボニル基(C = O)の変化は温度以外の要因も反映していることが分かり,興味深い.以下に赤外分光分析により得られた熱変成による IOM の変化[18] を少し詳しく紹介する.
様々なコンドライト隕石の IOM の赤外吸収スペクトルは,スペクトルの特徴に基づいて 4 つのグループ(A,D)に分けられた.グループ A は,芳香族 C = C に対して,O - H,脂肪族 C - H,C = O が多くみられることが特徴であり,熱変成を受けていないタイプ 1,2 の炭素質コンドライト(CR,CM,CI)が含まれる(図 5A).グループ B は,グループ A よりも上記の有機官能基の存在度がやや少ないことが特徴であり,弱い熱変成を受けたタイプ 3.0 の普通コンドライト,CO 炭素質コンドライトが含まれる(図 5B).グループ C は,芳香族 C = C に対してさらに他の官能基が少なく,芳香族 C = C 及び芳香族骨格のピークがシャープになっていることから芳香族構造の発達が見られることが特徴であり,熱変成を受けたタイプ 3.1 以上の普通コンドライト,CV3 炭素質コンドライトが含まれる(図 5C).グループ D は,グループ C と似ているが,C = O のピーク位置に明確な違いが見られ,タイプ 3.1 以上の普通コンドライト,炭素質コンドライト(CV3,CO3)が含まれる(図 5D).C = O に注目してみると,グループ A > B > C の順で芳香族 C = C に対する C = O の存在度の低下が見られ,グループ A,B に比べ,グループ C では C = O のピーク位置の高波数へのシフトが見られた.これは,熱変成により C = O の存在度が下がると共に,カルボキシルやエステルから,ラクトン型の構造(図 7)に変化した結果と考えられる.
Image Caption :
図 7. カルボキシル基,エステル結合,ラクトン型構造,及び不飽和ケトン型構造の例.
グループ D は最も低波数に C = O のピークがみられ(図 5D),不飽和ケトン構造(図 7)に由来すると考えられる.グループ C と D に属する隕石が経験した温度に大差はないため[24],これらの分子構造の違いは温度によるものではなく,酸化還元環境の違いによるものであると考えられる.したがって,グループ D に属する隕石は,比較的水の存在度が高い環境で熱変成を受けたために,脱炭酸反応などによりカルボキシル基が減少すると共に,新たに酸化されることにより不飽和ケトン型の構造が形成されたと考えられる.グループ C,D 共に CV コンドライトを含んでいることを考慮すると,これらの違いは同一母天体内における局所的な水の存在量の違いを反映していることが示唆される.
一方,IOM の H / C 元素比と水素同位体比(δD 値)の関係をみてみよう(図 6).CV,CO 炭素質コンドライト及びエンスタタイト・コンドライト(EC)は,H / C 元素比とδD値共に低い値を持っており,熱変成を受けていないコンドライト(CI,CM,CR)様の IOM が熱変成を受けることにより,H / C 比・δD 値共に減少したと考えることができる.しかし,普通コンドライト(OC)の IOM は,H / C 比の減少が見られるものの,高い δD 値を持っている[20,21].これらの違いは何を意味するのだろうか?
IOM の加熱実験の結果と比較してみよう.図 6に,Murray 隕石(CM2)の IOM の 300℃,6 日間[25],及び,Murchison 隕石(CM2)の IOM の 270,300,330℃,3 日間[26],それぞれの水熱実験結果を重ねてプロットしてある.いずれも,δD 値及び H / C 元素比の減少が見られる.一方,水を加えない不活性ガス雰囲気下における IOM の段階加熱(250 ~ 800℃)実験の結果,δD 値には顕著な減少は見られず,H / C 比が大きく減少している[27](図 6).まとめると,比較的低温・水の存在下では同位体比の減少が顕著に進み(図 6 において矢印の傾きが大きい),比較的高温・水の不在下では H / C 元素比の減少が顕著である(図 6 において矢印の傾きが小さい)といえよう.またこのことは,反応速度論実験の結果からも確かめられる.図 8 は,(a)Cody らの方法[13]をもとに重水素化して合成した模擬 IOM の水熱実験から求めた D / H 比減少のプロファイル[28],及び(b)Murchison 隕石の IOM を不活性ガス雰囲気下で加熱し,赤外吸収スペクトルの変化から求めた脂肪族 C - H 減少のプロファイル[29],を重ねてプロットしたものである.(a)と(b)を比較すると,300℃ 程度を境に低温側では D / H 比の減少が速く,高温側では脂肪族 C - H の減少が速いことが分かる.
Image Caption :
図 8. (a)Cody らの方法[13]をもとに重水素化して合成した模擬 IOM の水熱実験から求めた D / H 比減少のプロファイル(実線)[28],(b)Murchison 隕石の IOM を不活性ガス雰囲気下で加熱し,赤外吸収スペクトルの変化から求めた,脂肪族 C - H の減少のプロファイル(破線)[29].
以上を踏まえ,様々なコンドライトの水素同位体比(δD 値)と H / C 元素比との関係[20,21](図 6)を考えてみよう.まず,IOM の前駆物質は 2 章で述べたように星間空間起源の高い δD 値を持っていたと考えられる.また,H / C 元素比は一般に加熱により減少することから,IOM の前駆物質の H / C 比も高いと予測できる.したがって,IOM の前駆物質は図 6 において右上(おそらくグラフ枠の範囲外)にプロットされるであろう.低温の水質変成のみを受けた隕石は,H / C 比があまり変化せずに,δD 値が減少する(図 6:CR,CI,CM).おそらく,分子構造はあまり変化せずに,比較的 δD 値の低い水と同位体交換が起こったのであろう.引き続き熱変成を受けると H / C 比も減少する(図 6: CV,CO).一方,水質変成をあまり受けずに熱変成を受けると,δD 値はあまり減少せずに,H / C 比のみが減少する(図 6:普通コンドライト[OC]).このような過程を経て,図 6 にみられるような複雑な δD 値と H / C 比の関係に至ったと考えることができよう.なお,普通コンドライトの IOM にみられる高い δD 値は,議論の的となっており,金属鉄などが水熱変成により酸化され,母天体から水素が失われた際の同位体分別に伴い δD 値が高くなったとも考えられている[21].
3 - 3. 短期的な加熱による変成
南極で発見された隕石の中には,CM,CI コンドライトの特徴を持っているが加熱による脱水などが見られるものが多数存在する.Nakamura [30]はこれらの隕石を岩石・鉱物学的特徴に基づき,4 つの加熱ステージ:ステージ Ⅰ(< 300℃),ステージ Ⅱ(300 ~ 500℃),ステージ Ⅲ(500 ~ 750℃),ステージ IV(> 750℃)に分類した.これらの隕石は水質変成の後に,衝突あるいは太陽輻射熱等により,一般的なコンドライトが経験した熱変成よりも短期間の加熱を受けたと考えられている[31].このような CM コンドライトの IOM の熱分解ガスクロマトグラフィー分析の結果,加熱温度の高いものほど,熱分解生成物の量が少ないことが分かった[32].これは,高温を経験したものほど,IOMに含まれる側鎖や架橋構造が減少し,より芳香族構造が発達した結果,熱分解によって分離しにくくなったものと考えられる.このことは,Y - 86720 隕石(経験温度 > 750℃)の IOM の赤外吸収スペクトルに脂肪族 C - H や C = O があまり見られないことからも分かる[18](図 5C).また,加熱による H / C 比の減少も見られる[20,21,26](図 6:CM - H).しかし,熱履歴の指標とされるラマンスペクトルの G バンド位置・半値幅を見てみると,750℃ 以上を経験したと考えられる Y - 86720 隕石は,一般的な CM コンドライトの範囲内に収まっている[19].同様に熱履歴の指標とされる,C - XANES スペクトルのグラフェン構造に由来する励起子のピークも,Y - 86720 隕石にはあまり見られない[24].例えば 325 ~ 600℃ を経験したとされる Allende 隕石(CV 3.2 / > 3.6)[33]のラマンや C - XANES スペクトルと比べると,Y - 86720 の IOM はずっと始原的にみえる.さらに,WIS 91600(300 ~ 500℃),PCA 91008(500 ~ 750℃),及び Y - 86720 の C - XANES スペクトルの励起子のピークは,Vigarano 隕石(CV3.1 / 3.4,経験温度 300 ~ 400℃ [33])と比べると非常に低い[34](図 9).このような,ラマンスペクトルの G バンドや C - XANES の励起子は,いずれも芳香族の環状構造に起因し,これらの発達は IOM 中のグラフェン構造の発達度を示す.したがって,南極隕石などにみられる加熱を受けた CM コンドライトは,加熱時間が短期間だったことにより,長い期間熱変成を受けた CV や CO コンドライトほどにはグラフェン構造が発達しなかったと考えることができる.一方で,H / C 比や側鎖の減少は,短期間の加熱でも比較的速く進行するのであろう.
Image Caption :
図 9. WIS 91600(300 ~ 500 ℃),PCA 91008(500 ~ 750℃),Y - 86720(> 750℃),Vigarano(CV3.1 / 3.4)隕石の IOM の C - XANES スペクトル.図の出典[34].
3 - xx. Tagish Lake 隕石
もう一点特筆すべきなのは,2000年1月にカナダ西部の凍った湖に落下した,Tagish Lake 隕石である.隕石の一部は,数日中に手で触れることなく回収され,冷凍保存されたため,地球の物質による汚染の最も少ない隕石と言える.Tagish Lake 隕石は,一般的な炭素質コンドライトの母天体と考えられている C 型小惑星よりもさらに始原的な D 型小惑星起源であると考えられている[35].岩石学タイプは 2 だが,CI と CM との中間的な特徴を持っており,未分類の炭素質コンドライトとされている.最近,Tagish Lake 隕石の 4 つの異なる岩相(5b,11h,11i,11v)から分離された IOM の分析が行われた[36].それぞれの岩相の IOM の水素同位体比(δD 値)と H / C 元素比は,5b > 11h > 11i > 11v > Previous(以前の試料[20])の順に減少が見られ(図 6),母天体での水質変成度の違いを反映していると考えられている[36]. また,Tagish Lake 隕石の IOM(以前の試料[20])と WIS 91600(経験温度 300 ~ 500℃ の CM コンドライト)の IOM の 13C NMR スペクトルの類似が見られることなどから,これら隕石との関係性も指摘されている[34].Tagish Lake 隕石には,加熱を受けた CM コンドライトのような含水鉱物の脱水は見られないため,比較的低温での短期的な加熱を反映している可能性もある.
4. 有機物と鉱物との関係
最後になるが,IOM 研究において重要な点として,これらの有機物が独立に存在しているわけではない,ということが挙げられる.つまり,有機物は隕石中で共存する鉱物などの無機物質と密接に関わりあっており,その関係を無視することはできない.例えば,隕石中の有機物と粘土鉱物との共存関係が観測されている[37,38].また,IOM の模擬物質としてフミン酸を使った加熱実験から,サポナイト(粘土鉱物の一種)の存在下においては有機物の熱的安定性が増すことが分かっており[39],このような粘土鉱物が有機物を保護する役割を果たした結果,これらの周囲には有機物が残留しやすいことが示唆された.一方で,Murchison 隕石のバルク試料と IOM とで有機物の熱分解を比べると,バルク試料,つまり鉱物と共存している状態の有機物の熱分解の方が促進されたという結果もある[29].また,Murchison 隕石の透過電子顕微鏡による観測から,アモルファス炭素が硫化物の周囲を < 2 nm 程度の厚さで取り巻いていることが見られ,フィッシャー・トロプシュ反応により硫化物の周囲に有機物が形成されたことが示唆されている[40].
以上のような研究結果から鉱物種により有機物に及ぼす影響は様々であることがうかがわれ,今後個々の鉱物と IOM との関係性を系統的に明らかにしていく必要があろう.また,IOM と水との水素同位体交換を考えるときに,含水鉱物との同位体交換や分配も考慮すべきである[21].このような有機物と鉱物との関係は未だあまり研究が進んでおらず,今後は隕石中の有機物と鉱物の共存関係の詳細な観測を進めると共に,これら共存鉱物を含めた実験的研究が必要であろう.太陽系初期の物質進化過程の統一的な解明には,このような有機物と無機物質との関係性の理解が不可欠である.
5. 今後の展望
今後,さらに隕石コレクションやリターンサンプルコレクションが増えれば,パズルのピースを埋めるように初期太陽系での有機物の進化過程が解明されていくことが期待される.また分析技術の進歩と共に,隕石ほど多様な分析手法を適用できなかった,IDP などの微小試料からより多くの情報を得られるようになるだろう.
はやぶさミッションによるリターンサンプルからの画期的な成果[41-46]は記憶に新しく,後続のミッションが待ち遠しい限りである.特に,はやぶさ 2 ミッションは,有機物を多く含むと考えられる C 型小惑星をターゲットとしているため,まさに始原天体の有機物研究にはうってつけである.特に,(a)隕石有機物との類似性を直接確かめられる,(b)宇宙風化の影響を調べる,(c)地球上の有機物による汚染が最小限である,といった点において注目される.さらに,今後はより始原的な D,P 型小惑星をターゲットとしたミッションも検討されている.D,P 型小惑星起源と考えられている隕石は非常に少なく(先に紹介した Tagish Lake 隕石がその 1 つである),これらの小惑星からの試料が手に入れば,我々の太陽系始原物質に関する知識は飛躍的に向上するだろう.
謝辞
原稿執筆の機会を与えてくださり,また査読者として有益なコメントをして頂きました薮田ひかる先生(大阪大学)に感謝致します.筆者は日本学術振興会の支援を受けています.
参考文献
[1] 薮田ひかる,2010,遊星人 19,28.
[2] Derenne, S. and Robert, F., 2010, Meteorit. Planet. Sci. 45, 1461.
[3] Mueller, G., 1953, Geochim. Cosmochim. Acta 4, 1.
[4] Hayatsu, R. et al., 1977, Geochim. Cosmochim. Acta 41, 1325.
[5] Herbst, E. and van Dishoeck, E. F., 2009, Annu. Rev. Astro. Astrophys. 47, 427.
[6] Greenberg, J. M. et al., 1995, Astrophys. J. 455, L177.
[7] Ciesla, F. J. and Sandford, S. A., 2012, Science 336, 452.
[8] Ehrenfreund, P. et al., 1991, Astron. Astrophys. 252, 712.
[9] Millar, T. J., 2002, Planet. Space Sci. 50, 1189.
[10] Aleon, J., 2010, Astrophys. J. 722, 1342.
[11] Anders, E. et al., 1973, Science 182, 781.
[12] Nuth III, J. A. et al., 2008, Astrophys. J. 673, L225.
[13] Cody, G. D. et al., 2011, PNAS 108, 19171.
[14] Mumma, M. J. and Charnley, S. B., 2011, Annu. Rev. Astro. Astrophys. 49, 471.
[15] Loren, R. B. and Wootten, A., 1985, Astrophys. J. 299, 947.
[16] Kebukawa, Y. et al., Astrophys. J. 投稿中.
[17] Cody, G. D. and Alexander, C. M. O’D., 2005, Geochim. Cosmochim. Acta 69, 1085.
[18] Kebukawa, Y. et al., 2011, Geochim. Cosmochim. Acta 75, 3530.
[19] Busemann, H. et al., 2007, Meteorit. Planet. Sci. 42, 1387.
[20] Alexander, C. M. O’D. et al., 2007, Geochim. Cosmochim. Acta 71, 4380.
[21] Alexander, C. M. O’D. et al., 2010, Geochim. Cosmochim. Acta 74, 4417.
[22] Sephton, M. A. et al., 2000, Geochim. Cosmochim. Acta 64, 321.
[23] Pizzarello, S. and Williams, L. B., 2012, Astrophys. J. 749, 161.
[24] Cody, G. D. et al., 2008, Earth Planet. Sci. Lett. 272, 446.
[25] Yabuta, H. et al., 2007, Meteorit. Planet. Sci. 42, 37.
[26] Oba, Y. and Naraoka, H., 2009, Meteorit. Planet. Sci. 44, 943.
[27] Okumura, F. and Mimura, K., 2011, Geochim. Cosmochim. Acta 75, 7063.
[28] Kebukawa, Y. and Cody, G. D., 2012, 43rd LPSC, Abstract 1034.
[29] Kebukawa, Y. et al., 2010, Meteorit. Planet. Sci. 45, 99.
[30] Nakamura, T., 2005, J. Mineral. Petrol. Sci. 100, 260.
[31] Nakato, A. et al., 2008, Earth Planets Space 60, 855.
[32] Kitajima, F. et al., 2002, Geochim. Cosmochim. Acta 66, 163.
[33] Huss, G. R. et al., 2006, Meteorites and the Early Solar System II (Eds. Lauretta, D. S. and McSween, H. Y. Jr.), Univ. of Arizona, USA, pp. 567-586.
[34] Yabuta, H. et al., 2010, Meteorit. Planet. Sci. 45, 1446.
[35] Hiroi, T. et al., 2001, Science 293, 2234.
[36] Herd, C. D. K. et al., 2011, Science 332, 1304.
[37] Pearson, V. K. et al., 2002, Meteorit. Planet. Sci. 37, 1829.
[38] Kebukawa, Y. et al., 2009, Chem. Lett. 38, 22.
[39] 癸生川陽子,中嶋悟,2008,遊星人 17,232.
[40] Brearley, A. J., 2002, 33rd LPSC, Abstract 1388.
[41] Nakamura, T. et al., 2011, Science 333, 1113.
[42] Yurimoto, H. et al., 2011, Science 333, 1116.
[43] Ebihara, M. et al., 2011, Science 333, 1119.
[44] Noguchi, T. et al., 2011, Science 333, 1121.
[45] Tsuchiyama, A. et al., 2011, Science 333, 1125.
[46] Nagao, K. et al., 2011, Science 333, 1128.

Editor : Akira IMOTO
Editorial Chief, Executive Director and Board of Director for The Planetary Society of Japan